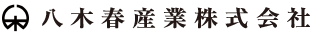我々は商人道を原理原則として掲げていますが、商人道とは何か理解を深める必要があります。そもそも士農工商の身分制度のあった江戸時代に石田梅岩が商人の儲ける事の正当性を説いたものですが、「三方よし」筆頭に具体的に現場で実践できないといけません。
日本は物質的に豊かで格差も比較的少なく、財布を落としても戻ってくるぐらいの国民性ですが、海外ではそれはありません。それどころか、隙を見せるとやられてしまいます。また実は日本の商売でもグローバル化が進み、商売はお人好しでは上手くい気ません。
そもそも日本人は建前と本音が違うケースも多く、当たり障りのない事を言って曖昧にします。元々契約社会でなく明文化が下手です。言わなくても分かるという暗黙知でやってきた社会だったのです。しかし、現代社会は違います。言わないと分からないものと言って主張する世界になりました。
大阪、特に船場は好きですが、経済的には変化に取り残された感があります。それでも「利は元にあり」という商売原則が残っていたり、近江から商人道が伝わった元商都です。前回の万博が開催された1970年は、大阪は絶頂期でした。
しかし、今や繊維中心に面影はなく、今年の万博は今後どうなるか楽しみな分岐点になりそうです。
ところで一対一の対応だとか、ダブルチェックだとか今や当たり前の原則がありますが、案外知らなかったり出来ていないものだと再認識しました。物と伝票を一対一で動かし対応するのが一対一の対応原則ですが、伝票を怠ると会計がおかしくなります。
またダブルチェックは今更ですが、一人でやれる環境を作っては不正の温床になります。これは人を信頼しないとかいうレベルの話ではなく、人に不正を犯す環境を作らない思いやりの原則です。現金と記帳は別の人がやる、仕入と販売も別の人がやる、これは商人道と言えるのでしょうか。当たり前かもしれません。
東京と大阪を行き来する中、海外事業も国内事業も更に前に進んでおります。変化に対応しないといけませんが、原理原則は守らないと足元から崩壊します。そもそも儲かってなかったら続けられないのも原則ですが...